
編集長の読書日記 其の一
2月某日
今日は立春。これからは春である。
「春風や 言葉が声に なり消ゆる」は池田澄子の句。
『ペンギンブックスのデザイン 1935-2005』(フィル・ベインズ 著、 山本太郎(アドビ・システムズ) 監修、齋藤慎子 翻訳、ブルース・インターアクションズ)を眺める。タイトル通り、ペンギンブックスの初期から2005年までの表紙のデザインと、その歴史についての本。
創設当初、ペンギンをシンボルに決めるやいなや、社員に動物園まで写生しに行かせる(そして、それを実際に表紙に利用する)話など、創設初期の行き当たりばったり感が微笑ましい。素晴らしい表紙のデザインばかりで、付箋でいっぱいになってしまった。配色のバランス、佇まいが一貫して背骨がしっかりしている。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
『猪谷六合雄―人間の原型・合理主義自然人』(高田宏著、平凡社)読了。
猪谷六合雄について「自然を愛し、自分でなんでも作っていた人」位しか知識のないまま手にとる。読みすすめてわかったのだが、彼は一般的には日本のスキー界草分けの人物として知られているようだ(息子は日本人で初めての冬季オリンピックメダリスト、猪谷千春)。
それも誰に習ったわけでもなく、自分の家の旅館に泊まりに来た客(彼は赤城温泉の旅館の生まれ)の持っていたスキー道具を見て、見よう見まねで自分用のスキー板をつくってしまう。そして山を滑っていた時に、目の前にあった薪の山を飛び越えたら気持ちが良くなって、スキージャンプを自己流で極めてしまう。
とにかく、バイタリティに溢れた人物だ。70歳を超えてから自動車の運転免許を取得すると、今度は車を改造して移動手段兼住居にして、あちこちに出かけてしまう。
自然に魅せられて、臆さずその中に飛び込んでしまう彼の目に映る世界は、ものすごく純度が高かったに違いない。「生きることが仕事」という言葉が本文中に出てくるが、本当にその通り。そもそも「貧乏になることを恐れない」猪谷の思考は軽やかで、朗らかだ。悩む、ということがほとんどない。
なんというか、頭の中にまで、山の冷たく清らかな風が吹いているような人だな、と思う。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
集落について議論しているにもかかわらず、実物を見たことのない著者たち研究室グループが、世界中の集落を見て周る。「未来のために一枚の建築や都市のスケッチを描く」という目標を持つ旅の記録だ。したがって「世界にはこんな人もいた、あんな場所もあった。すごかった」という旅エッセイではない。建物の写真や絵が最小限に抑えられているため、細部まで想像するのは難しかったが、行く先々での人々の反応、交流などを楽しく読む。
著者は、最後に「場所」や「地域」を中心概念として文化に対峙するための視点を示している。それは、相互の文化の共有関係に目を配ること、場所を生体的秩序としてとられる全体観を捨て意味ある部分の自立性を認めること、そして、局所的な自然に対する仕掛けの考案はいつでも要請されてきたことを認めることの3つ。これらは、先週、『異端の数ゼロ』の簡略化した西洋と東洋の対比に違和感を持った私が、最も欲していた回答のように思う。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
『精選女性随筆集八 石井桃子 高峰秀子』(川上弘美編、文藝春秋)読了。
読み終えてまず感じたのは、この2人を組み合わせたのがすごいということだ。
石井桃子の随筆は、浦和の町で家族と過ごした幼少期のものが中心。大家族の末っ子として育った石井の描く世界は、自分よりも年上の者たちの間から通して見える世間の様子だ。
それに対し、高峰秀子のそれは、映画界のスターたちと過ごした家の外でのものである。経済的には自分が家族の生計を立て、しかしその家族も血のつながりがない、という高峰のえがく世界は、自分と世間の中からいつの間にか紡ぎ出される人間関係なのだ。
とことん正反対の目線が、この本を読み進める読者の中で交差していく。
編者の川上弘美は、2人の共通点として「随筆を書くこと以外に大きな仕事を持っていた女性」であること、「彼女たちのエッセイは断片ではない/それらが集まった一冊は、彼女たちの人生をそのまままるごと担っている」という2つを挙げているが、それ以上に、組み合わせの妙というものが作り出した豊かさがこの本の中に詰まっている。
それにしても、幼少期のエッセイというものは、どれも共通して、子供特有の気軽さと不自由さがマーブル状になっている「あの感じ」を思い出させる。子供であったがゆえにかかざるをえなかった恥の数々が、私の心の中を走り回って、私はじっとそれらが走り去るのを待つ。
○ ○ ○ ○ ○ ○
私は、その時々でピンときた本を5~10冊用意して、その中でも自分のバイオリズム(?)に最も合致する本から読んでいく、というタイプなのだが、今週は「のぞき見根性」丸出しの週だったように思う。ここに挙げた本以外に、『須賀敦子全集 第4巻』(須賀敦子著、河出書房)をパラパラと再読し、『定家明月記私抄』(堀田善衛著、筑摩書房)を読み始め、『流しのしたの骨』(江國香織著、新潮社)をぼんやりと頭の中で再生し続けた一週間だった。誰かの生活をのぞき見するのは、とても楽しい。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
『私自身の見えない徴』(エイミー・ベンダー著、管啓次郎訳、角川書店)読了。
ときおり、はじまりの1文目からこちらの負けが決まっている本がある。
衝撃的なラストに呆然とするといったタイプではなく、なんというか「この本には太刀打ちできない」という敗北感を抱くようなパワーを持っている本。そういった本に対して批評性を持つのは難しい。ツルツルの氷山に素手で立ち向かうようなものだ。(結局、自分の力不足に行き着く)
この本もその1つ。
木をノックすることと数学を愛し、小学校の数学教師になった主人公モナ・グレイ、医者だったのになぜか「色あせて」しまった父、高校の数学教師をやめて金物屋をしているジョーンズさん、腕にやけどのあとがびっしりとある理科教師ベンジャミン・スミス、そして奇妙な教え子たち―
とにかく、出てくる人物がすべて、ずれているのだ。そしてすれ違っている。その悲しさや、戸惑いに溢れている、ように思う。(いかんせん太刀打ちできないので、弱腰)
例えば、モナが自分の20歳の誕生日に、ジョーンズさんから斧を買う場面。
“金物屋で斧を買ったとき、それを持って歩くのが楽しかった。木の柄をふりつつ、家のどこに置こうかなと考えながら。日陰になった歩道をぶらぶら歩き、心の中でいろんな部屋を試していった。ベッドの下に置いておこうか?タオルかけにかけておく?食器引き出しに押しこんじゃう?仕事から家に帰ってきたらまず斧に挨拶する、クローゼットを開けてこんにちは、きれいな道具ちゃん、と声をかけるのだ。新しい靴を買ったとき、クローゼットの中でじっとおとなしくてぴったりの機会が訪れるのを待っててくれるそれに声をかけたくなるのとおなじように。”
何もかもが、こんな感じですすんでいく。魅力的な物語。圧倒的な世界。
こういった本との出会いが、幸せということなんだと思う。本当に。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
紀行文や旅日記は好きな方だと思う。
私自身は人ごみ嫌い、旅行の準備嫌い、乗り物嫌いと全く現実の旅行には向いていない性格だ。
どこか遠くに行きたくなった時はまず、本棚から旅行の本を取り出す。ページをめくれば、私よりももっと旅行に適した人が見た世界が広がっている。その行間に数時間だけお邪魔してくる。1番贅沢だ。
この本は、オセアニアとアメリカ、時たまヨーロッパや日本、中国などの紀行文だ。
面白かったのは、著者が研究休暇のためにニュージーランドに住んだ時の話。一般的に、旅の記録は、生活という反復を許さない、と著者は主張する。反復を許さない、ということは生活の描写を許さないということだ。非日常の中での出来事しか文章として残らない。そこで、著者はニュージーランドでの生活という反復を描写する。(「素晴らしい反復だった」という、その生活)
旅に関する文章は、必ず「視覚に訴える」文章(空の色、建物の形、風景)、「嗅覚に訴える文章」(土地の空気の匂い、人々の体臭)のどちらかに分かれる。この本は前者。場の要点をつかもうとする著者のシンプルな文章が、頭の中で立体的な風景となって立ち上がってくる。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
今週は、面白い本をあまり読まなかったので、代わりに買った本を紹介しようと思う。

左から、『20世紀ボックス Package Design History』(木村勝著、六耀社)、『泉に聴く』(東山魁夷著、講談社)、『一生一色』(志村ふくみ著、講談社)
東山魁夷と言えば『川端康成と東山魁夷―響きあう美の世界』、志村ふくみと言えば読売新聞の時代の証言者が気になる今日このごろ。しかし、注目はやはり、1番左のヤツだ。
生活に欠かせないありとあらゆるパッケージから、厳選した400点を集めた20世紀の箱図鑑。
この本でしか見られない希少な商品もあるらしいが、全体的に目が離せない・・・。
例えば、

雛菓子なんて存在、初めて知った。デコスイーツの先祖に違いない。

どちらさま?

お茶目さのかけらもない。
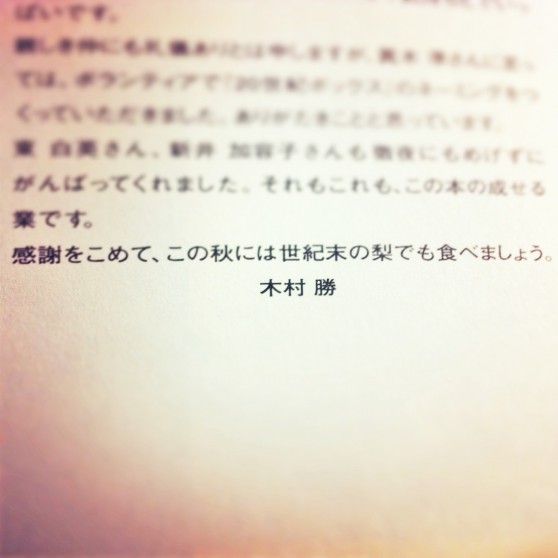
1998年の梨は、美味しかったのだろうか。
ものすごくおすすめの本です。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
『ピダハン「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L.エヴェレット著、屋代通子訳、みすず書房)読了。
言語学者兼キリスト教の伝道師の著者が、アマゾンの奥深くに住むピダハンとともに20年過ごした記録。先日、NHKでも番組が放映され、話題となっている1冊。
敬虔なキリスト教信者の著者は、今まで言語学者の誰も身につけたことのないピダハン語を習得するため、集落に飛び込む。それだけなら若き言語学者の熱意と理解できるのだが、なぜピダハン語を学ぶのかというと「聖書をピダハン語に訳すため」というのだから(そもそも彼の研究費は聖書の翻訳と伝道を目的とする団体SIL internationalから出ている)二重のカルチャーショックを受ける。
著者はピダハンの特徴を、いくつか挙げている。
まず、彼らは子供も大人も区別をしない。子供は保護の対象とはならない。そのため赤ん坊が包丁を手に遊んでいても制止しない。赤ん坊が怪我をしたら、それは止めなかった大人ではなく、赤ん坊自身の責任なのだ。
また、ピダハンは「自分の人生は、自分で落とし前をつける(つけさせる)」という態度を徹底している。例えば女性の出産は死の危険を伴うものだが、女性たちは川辺や木陰で、大抵ひとりで子供を生む。出産時に危険な状況になっても、誰も助けにはいかない。そのような状態から生まれた子供が医療の発達していないピダハンのコミュニティーで健康に育つ見込みは皆無だと、最初から知っているのだ。
そして最も重要な特徴は、ピダハンは自分たちの見たことしか信じない点だ。著者からピダハン以外の文明社会の生活や信仰の話を聞いても、自分たちの生活に反映させようとはしない。それが自分の生活の向上につながるとしても、だ。反面、妖精や霊は信じる。彼らは日常的にそれが見えるらしい。
最終的に、ピダハンたちへのキリスト教の布教は失敗に終わる。ピダハンには神にすがるような悩みなどないし、そもそも同胞の誰も見たことのない神など信じることはできない。そして、ピダハンと共に生活するうちに、著者も無神論者になってしまうのだ。
ピダハンの哲学は、私たちのそれとは違いすぎる。その差異はどこまで行っても平行線のままだ。そして、ありきたりな言葉になるが、ピダハンは何も持たず、死が身近にあるがゆえに私たちよりも強い。
文明は私たち人間にとって重荷なのかもしれない、と考えさせられる。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
私は味に頓着がない。味そのものよりも、食事をする環境の方が気にかかるのだ。
ここは落ち着いて食べられる場所なのか、私は食事をするほど空腹なのか、一緒に食事をする相手は、進んで食事を共にするほど親しい人なのか(親しくない人との食事ほど辛いものはない)・・・などなど。
それらがクリアできていれば、あとは何も考えずに咀嚼し、消化するだけ。そもそも、噛む回数が少ない。直そうと何度も試しているが、なかなか難しい。せめて、本の中だけでは食事を味わいたい。そんなときには食事に関するエッセイがうってつけだ。
著者は、おおらかに料理を全般的に楽しむ。全般的に、というのは料理のジャンルもさることながら、調理すること、食事をすること、料理を介して人と出会うことだ。どの話も、その料理を食べた場所や時間への慈しみ、調理のポイント、そして彼女の料理に対しての好意で溢れている。
1番好きなのは、著者が幼少期に、風邪をひいたときにおばあさんが作ってくれたうどんの話。秘伝のレシピだから本には載せられない、という断りも素敵だ。
○ ○ ○ ○ ○ ○
2月某日
『チボー家の人々(1)灰色のノート』(ロジェ・マルタン・デュ・ガール著、山内義雄訳、白水社)再読。高校生の頃に読破したはずなのだが、内容をすっかり忘れている。
資産家のカトリック教徒で、高圧的な父、優秀な兄の下、日常に不満だらけのジャック。
貧しいプロテスタントで、優しい母、病弱の妹に囲まれ、優等生のダニエル。
この巻では、対照的なふたりが家出を企て、実行し、家に連れ戻されるまでが描かれている。
サブタイトルの「灰色のノート」は、家出前、ジャックとダニエルが手紙代わりに利用していたノートのことだが、その内容に驚く。作中の設定は1920~1921年。あの頃の14歳は、随分大人びていたのだろうか。今時の男の子は「僕には君しかいないのだ!」と書いたり、自作の詩(それも古典をベースにした)を添削しあったりできるとは思わない。
それとも、これは当時の中二病というやつだろうか・・・。とくにジャックは、反抗期真っ只中の、無防備で、無鉄砲で、感情の起伏が激しいナイーヴな男の子。家出を発案したのも彼だ。反抗することでしか周囲の大人とコミュニケーションが取れない。それでいて、いつでも自分を理解し甘えさせてくれる人を探している。
家出先のマルセイユではラストを暗示する(?)場面も描かれている。11巻まである大作なのでゆっくりと楽しみたい。
ちなみに、高野文子さんの作品に『黄色い本 ジャック・チボーという名の友人』という漫画がある。これは『チボー家の人々』を読む女の子の話。こちらも素晴らしい作品なのでぜひ。
writer profile
1992年生まれ 後楽園⇔神楽坂他 ドリフターズ・マガジン編集長